コンサルタントとして第一線で活躍する榊巻亮さんの著書「世界で一番やさしい考え方の教科書」を読み終えました。
明確な正解のない課題に向き合うビジネスマンはもちろんのこと、
変化の激しい業界で働くエンジニアにとっても日々の業務で活かせる内容だったのでまとめました。
どんな本か
仕事をする上で、考えて成果を出すということを毎日のように求められます。
しかし肝心の「考え方」にはついて体系的に教わる機会はあまりありません。
本書は主人公である中堅社員の葵(あおい)が、社内の請求書を標準化するプロジェクトを任される物語形式になっています。
初めてプロジェクトをリードする立場に困惑し、思考停止気味の部下にイライラしながらも、凄腕コンサルタントの父から「考え方」を教えてもらいプロジェクトを進めます。
この本は「考え方」が言語化され、体系的に学ぶことができます。
業界や職種を問わず、全ての物事に応用できる考え方を学べる良本なので、就職活動中の学生や全ての社会人におすすめの一冊です。
考え方の循環サイクル
本書では、考えるとは「認知」「思考」「行動」という3つの動作を循環させることだと結論づけています。
考えるというと思考する単発の行動をイメージしがちですが、この考え方の循環サイクルを高速で回すことこそが考えるということなのです。
ビジネスの世界では学校のテストと異なり明確な答えがありません。
なので一発で相手が求める期待値の合格点を取るのが困難なため、この考え方の循環サイクルを回すことで仮説を段階的に合格点に近づけていく必要があります。
では、それぞれの動作で何をするべきか見ていきましょう。
認知する
思考するためにその事象を正確に捉える必要があります。
この認知を間違えると、思考の方向性を誤り、間違った仮説が立てられてしまいます。
そうならないため、言葉→状況→意図の順番で認知すると良いでしょう。
言葉の認知
認知というと「相手の意見を黙って聞いて理解する力」と思われがちですが、むしろ質問することが認知の肝になります。
質問することで相手の言葉に含まれるあやふやな単語や曖昧な文章を明確にして、認知を深めます。
状況の認知
質問して言葉の認知ができたら次に状況の認知です。
相手の言葉からその状況が疑似体験できるようイメージします。
それほど具体的な状況を想像しながら話を聞いていると自然と質問が出てくるはずです。
状況の認知をする際のコツ
・主語と目的語を明らかにする
・事実と思いを切り分ける
意図の認知
最後に意図の認知をします。
コミュニケーションには必ず意図があるのでそれを自分の言葉で確認します。
最終的に認識のズレをなくせれば良いので「〜というふうに受け止めましたが、認識は合っていますか?」というように意図の確認をします。
これら言葉、状況、意図の3つが確認できて初めて認知ができたと言えます。
思考する
事象を正確に認知したら次は思考します。
事象に対して20点の完成度で良いので仮の答えを出します。
スムーズに思考を行うために以下の手順があります。
1 問いを書き出す
2 考えるべきことに順番をつける
3 問いに対する答えを出す
4 「具体的には?」「なぜ?」で思考を深める
それぞれ見ていきましょう。
問いを書き出す
何について考えるべきか整理できていないまま思考を始めるとすぐに脳が容量オーバーになります。
そうならないために考えるべきことをToDoリスト改めてThinkリストのように箇条書きします。
考えるべきことに順番をつける
Thinkリストの箇条書きができたら思考するべき問いに優先順位をつけます。
この作業を紙などに書き出すだけで脳が整理され、次のステップがやりやすくなります。
問いに対する答えを出す
ここに来て初めて思考することができます。
しかし、思考はあくまでもサイクルです。
ここで行う「問いに対する答え」は結論ではなく「多分こうなんじゃないかな?」という現時点での仮の答えで良いのです。
ここで結論を急いでしまうと行き詰まります(葵も正解を出そうとして手が止まってしまいます)。
「具体的には?」「なぜ?」で思考を深める
現時点の仮の答えに対して「具体的には?」と「なぜ?」と問いかけることで思考を深めます。
「具体的には?」で自分の思考に対して曖昧さをなくし解像度をあげます。
「なぜ?」と問いかけることで自分の思考に対して理由づけをして論理を通します。
実はこの4つ目のステップはサボろうと思えばサボれてしまうが、
思考力が高い人は無意識に行っている重要なステップだと著者は書いています。
これを行わないと「なんとなくそう思った」だけの粗い思考をアウトプットすることになるからです。
行動する
思考をするとどこかで行き詰まります。
行き詰まると多くの人が「考えているようで悩んでいるだけの足踏み状態」に陥ります。
これは一見考えてるようで実は何も進んでいません。
そこで思考の停止を打破するのが行動することです。
以下の状態になったら思考から行動のステップに移るサインです。
足踏み状態のサイン
・ペンが止まる
・資料の微調整を始める
・20分経過(人が思考できるのは20分が限界なため)
足踏み状態のサインに気づいたら行動することで現状を打破します。
具体的にどんな行動をとるべきか見ていきましょう。
足踏み状態を打破する行動
- 誰かに相談、壁打ちすることで話す
- 情報収集やヒアリングして思考材料を集める
- 脳をリフレッシュさせるために休む
話す、集めるはイメージしやすいですが、最後の休むことも行動の一つです。
休むという行為は散歩やシャワーを浴びる、掃除をするなどして何も考えない状態を作ることです。
脳は体力がないので休ませることで情報を整理します。仕事から離れたときにふとアイデアが浮かぶときがあるのはそのためです。
コールアウト
休むのが有効なのはこれまでの手順を踏んでしっかり思考されたときです。思考されてない時に休んでも体力が回復するだけです。
前述した通り思考するというのは、単発の動作ではなく、認知→思考→行動を回すサイクルです。
行動して新たに得たヒントや手がかりをもとに現状を認知してから思考し、行き詰まったらまた行動するサイクルを繰り返すことで仮で出した答えの精度を上げていきます。
洞察する
洞察は、考え方の循環サイクルとは別軸で存在する思考です。
考え方の循環サイクルを同じ対象に行ったとしても新人とベテランがやるのでは出てくるアウトプットは異なります。
なぜなら新人とベテランとではいままでの経験から得た知識、感性、勘による力の差があるからです。
この知識や経験をより多く得るために洞察があります。
認知、思考、行動を回す考え方の循環サイクルが目的を達成するための縦の思考だとすれば、
洞察は循環サイクルの質を上げる横の思考だと言えます。
具体的には、考え方の循環サイクルの対象に対して、「ここから何が言えるのか?」と示唆や教訓を得たり、「相手の立場だったら?」と相手になりきったりすることで、物事の見方を広げて縦の思考の質を底上げします。
洞察力は普段からニュースを見たり読書をしたりするなかで、「この情報を見た人の行動はどう変わるんだろうか?」「この情報はどの程度信ぴょう性があるのだろうか?」と考えることで磨かれます。
まとめ
単発で思考だけをするのは多くの人が既にやっているのではないでしょうか。
ただ、問題を認知せずに思考だけをするから適切な解決策が出てこず不安に陥り行動にも移せない。
そんな人も多い気がします。
「行動しろ」と結論づける自己啓発本が多いなか、「考える」方法についてまとめられた本は少なく、中でもこの本は誰でもわかりやすい物語形式で体系的に考え方を学ぶことができます。
明確な答えがない不確実な世界に生きるすべてのビジネスマン、特に変化の激しいIT業界で働くエンジニアにとっては基礎となる本だと思います。

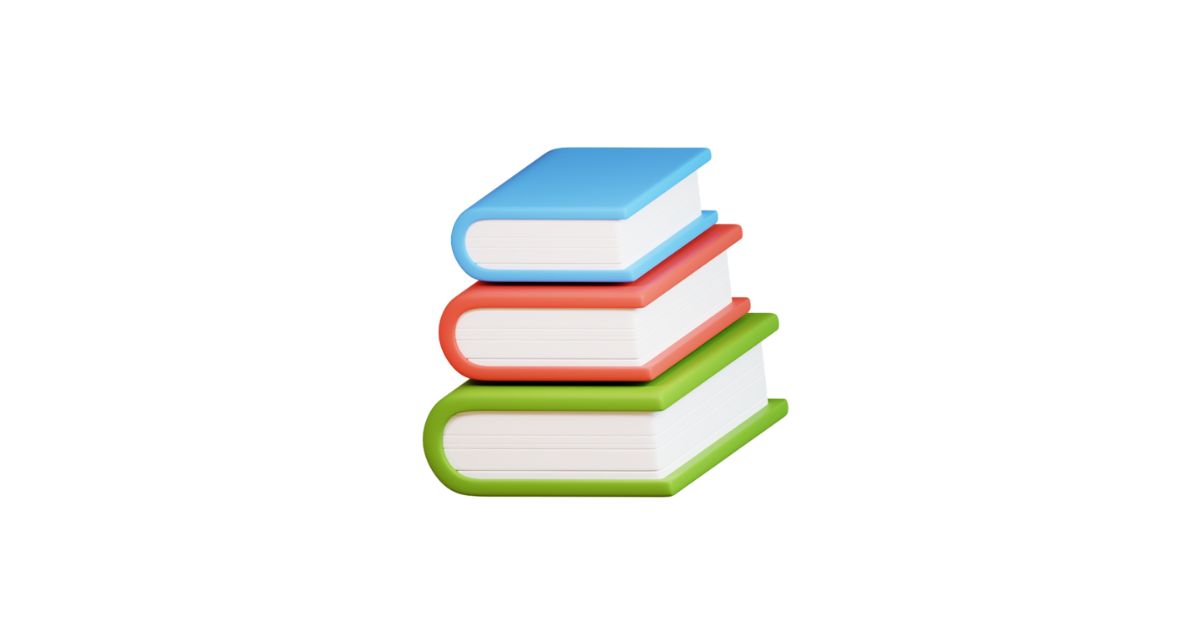


コメント